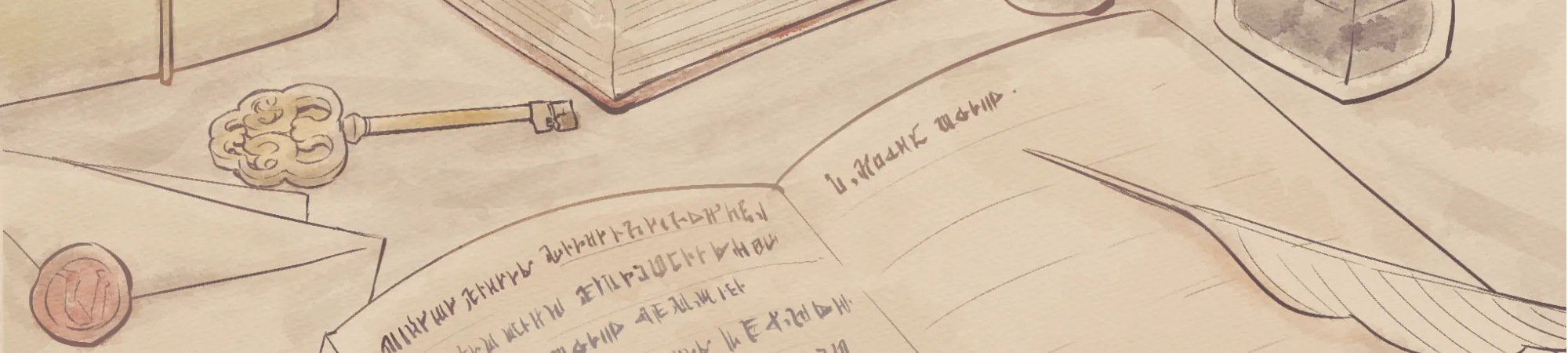※サイラス先生は料理ができない、という独自解釈あり
※本編終了後にナチュラルにアトラスダムで同棲してる
※食べ歩きデートしてるだけ
「キミの好きな食べ物を知りたいな」
帰宅早々サイラスは唐突に、にこやかに聞いてきた。
アトラスダムにあるオルブライト宅。長い8人での旅を終え、テリオンはここでサイラスと共に過ごしている。
テリオンの隣には、いつの間にかサイラスがいるのが当たり前になっていた。放っておいてもペラペラとしゃべり教鞭を執り始める変な学者先生。出会った当初はそう思っていたのに、離れがたく感じるようになったのは一体いつの頃からだったろうか。
旅の終わり、テリオンは胸の内をサイラスへ告白した。あんたと、共に在りたいと。その意味を鈍感なサイラスが理解して受け取ってくれるまで、それはそれは、かなりの時間と労力を費やしたのだが……そこは割愛しよう。これ以上語ると学者先生の講義より長くなってしまう。
ともかく今は二人で暮らしているのだ。お互い”平穏”の二文字とは縁遠い男であったから、波乱の日々ではあったが。サイラス的に言うのなら『毎日新しい発見のある飽きのない日々』を共に過ごしていたのだった。
「あ、リンゴ以外で頼むよ。それは知っているからね。肉とか魚とか。キミは何でも食べるが、好き好んで食べるものを知らないと思ったのだよ」
そう聞かれても、食い物の選り好みをできる環境で育ったわけではないテリオンには、特別好きな食べ物などなかった。
「……別に好みなんてものはない。食えればその辺の草だろうがフロッゲンの肉だろうが食うさ」「フロッゲンの肉……! そういえば鳥肉と同じ味がすると聞いたことがあるな……」
「やめとけやめとけ。あんたが食ったら腹壊しそうだ」
やれやれとテリオンは首を振る。サイラスの好奇心を刺激してしまい話が脱線した。好きな食べ物を知りたいと突然言い出した発端があるはずだ。
「……で、本題はなんだ?」
「ああ、これだよ。町でポスターを見かけてね」
「グランポート美食祭……?」
サイラスが手渡したのはチケット風の紙切れだった。木版単色刷りであろうそれには野菜や魚の絵と共に、祭りの日時が綴られている。
「ああ、東西南北あらゆる地方の料理が集う催し物みたいだよ。大陸外からも料理人や商人が来るらしい。フラットランドからも特別便の船が出るから、今度の休日どうかな?」
「……調査以外で遠出を提案するなんて、珍しいな」
「調査といえば調査になるね。キミの好物を知る調査だ。それにこの祭りに行きたい一番の理由は……キミにいつも料理を任せてしまっているから、たまには美味しいものをご馳走しようと思って……ね」
サイラスは少し面目なさそうに語尾をすぼめた。
「ああ……あんた、まさか全く料理できないと思わなかったからな……」
「う……キミと暮らし始めるまで、自炊できないことが不便だとは思わなかったんだ」
アトラスダムの街には食堂も酒場も豊富にある。例え料理ができない、する時間もない男が一人で暮らしていても何も困らなかった。旅の最中も酒場料理や携帯食で済ますことが多かったから、サイラスが料理らしい料理をすることはなかった。
しかし二人で暮らすとなると気ままに外食したり、適当にサンドイッチで食事を済ますわけにもいかない。
最初は家主であるサイラスがキッチンに立とうとした。だが、サイラスが行うのは調理というより実験になってしまうのだ。分量通りに作れば良いというのに、生来の好奇心で色々なものを試しに入れてしまい、高確率で摩訶不思議な物体が出来上がってしまうのだった。
それにはテリオンもさすがに顔が引き攣った。
『あんたがキッチンに立つと変な調味料だらけになるし、いつか絶対火事になるぞ』
そう釘を差したテリオンだって凝った調理はしたことがなかったが、持ち前の器用さでサイラスよりはマシな料理を作ることができた。だから最近は食堂に行くよりも、テリオンの手料理を二人で食すことが多くなっていた。
今日もウォルド産の赤ワインで煮込み料理を作りながら出しっぱなしの本を片付けていたが、同じことをサイラスがすれば火事になるだろう。鍋を放置して、間違いなく。
ちなみに今日はたまたま家にずっといただけで、テリオンはサイラスの家政夫じみたことをしているわけでない。サイラス経由で舞い込んでくる、王立学院で使用する研究資材の調達が今の仕事だ。
「――それで、キミの意見はどうだろうか?」
「まあ……あんたが興味あるというなら、行く」
「決まりだね。キミ自身も知らない好みを知ることができる……ふふ、楽しみだ」
◇◇◇
グランポートへ向かう特別便は、天候にも恵まれ滞りなく運航した。
船から降りた瞬間から、食欲をそそる香りと賑わう人並みに埋め尽くされた。グランポートの露店街は普段なら武器屋や雑貨屋もあるが、今日出店しているのはほとんどが飲食店や食材店だ。
「おお、これは東国の織物だね。魚の文様とは珍しい……実に興味深いね」
「おいサイラス、食いに来たんだろ」
波止場のそばに出店していた鮮魚店らしき屋台で、さっそく物珍しいものを見つけたサイラスの足が止まった。テリオンが窘めていると、店主の男に声をかけられた。
「ハハハ、学者さん、それは店の暖簾だから売れないが魚はどうだい? この場で食っていけるよ」「ふむ、並んでいるのは全て生魚のように見えるが。焼いてくれるのかい?」
「東国では生で食うんだよ。これは今朝ここいらの海で採れた新鮮な白身魚を捌いたもんだ。塩で食べると美味いよ」
「……生とか怖くて食えんな」
「ほうほう、ものは試しだね」
テリオンは怪訝そうな顔をしたが、サイラスは揚々と白身魚を薄く捌いたものを購入した。
「なるほど、新鮮な生魚とは弾力があるのか。焼き魚のホロホロする食感とはまた違って、歯ごたえがいいね」
食あたりでもしたらどうするんだ、とテリオンが拒否感を示すのをよそに、サイラスは食感を楽しんでいる。
「テリオンも食べてみるといい」と差し出してくるものだから、渋々ながら一切れだけ食べてみた。弾力がある、とサイラスは表現したが、もにゅっとした食べ慣れない食感だ。
「……淡白すぎてよく分からん」
「私はこの奥ゆかしい旨みが良いと思うけれどね。生魚はお気に召さなかったか……あ、酒屋があるよ」
「酒なら飲む」
サイラスの目線の先には、酒樽と瓶が並んだ屋台があった。そこでもまた、店主であろう商人の男に声をかけられた。
「兄ちゃん達、ブラックエールはどうだい?」
「ブラックエールとは?」
「麦芽を黒くなるまでローストしてんだよ。ほいよ、試飲だ」
試飲用にと小さめのグラスを渡され、エールが注がれた。琥珀色の見慣れたエールとは違い、黒々としている。飲んでみると、見た目によらず口当たりがスッキリとしていて喉越しもいい。
「ほう、芳ばしいのはそのためか……これはどうだい、テリオン?」
「……たまに飲むならアリだな」
「暖かい料理に合うぜ。どうだい一本?」
「一瓶買っていこうか」
「ああ」
「では取り置きを頼みたい。帰りに取りに来るよ」
「まいど! 持ち帰り用に包んどくよ」
それからサイラスの興味が赴くまま露店街を歩いた。テリオンは学者のローブが揺れる様を追いながら後ろをついていく。
パン屋、肉料理屋、青果店、菓子店など、店の系統も様々だ。サイラスは珍しいものを見かける度に立ち止まり、試食や店主の話を楽しんでいた。正直テリオンは見たことがない食べ物は味が想像できず、あまり興味が湧かない。目移りしながら露店を巡るサイラスを見るのが面白いから、ついて歩くのが嫌なわけではなかったが。
小一時間ほど経ったところで、サイラスも当初の目的を達成していないことに気付いたらしい。
「ううむ……キミの好みを知るために来たはずだったのだが」
「あんたがほいほい先に行くからな。それに、食ったことないものは警戒する」
「そうか……未知に踏み込むというのは学びには大事なことだが、キミの警戒心は経験に基づくものであるからね。否定はしない。……ならば、別行動でそれぞれ好きなものを買って来るのはどうかな?」「ああ、それでいい」
「では大競売場のそばで落ち合おう」
露店街から少し離れた大競売場のそばには、飲食スペースとして簡易なテーブルとベンチが並んでいた。テリオンが先に買い物を済ませ場所取りをしていると、すぐサイラスもやってきて向かいの席に腰掛けた。 お互いに好きな酒とパンや肉料理やスープ、菓子など買ってきた数品をテーブルの上に並べた。
「酒のつまみにリバーランド産の川豆はどうだろうか」
「つまみか、微妙に被ったな。俺はウッドランド産のミックスナッツだ」
「まあ日持ちするものだからね。余ったら持ち帰れば良いさ」
でも好みが被るというのは嬉しいものだね、とサイラスは微笑む。それからテリオンが手に持っている料理に興味を示した。
「キミのそれは何の肉だい?」
「ハイランドの羊肉らしいが……ソースが美味い」
「ほう、羊か」
「食うか?」
「じゃあ一切れ頂くよ」
テリオンが串肉を差し出すと、身を乗り出して肉の一欠片を口に入れた。こいつ、俗にいう「あーん」という構図になっているのを分かってやってるんだろうか。分かってないだろうな。
「ふむ、確かにソースがいいね。オニオンと……ガーリックも少し入っているかな。アリウム野菜で羊独特の臭みを消しているのだね」
「アリウム?」
「オニオンとガーリックは植物分類上、仲間だよ。球根があり、独特の臭いを持つこれらをアリウム属という」
「球根……ああ、食うところはどちらも根っこか」
「そのとおりだ。家に植物図鑑があるから、帰ったら読んでみるといい。図鑑を眺めるのも楽しいよ」
料理は下手でも舌は確からしい。そこはさすが、王城に出入りする身分の人間であるからだろう。それに加え、頭の中の知識と結び付けて食材を言い当てるのだから学者先生は伊達ではないのだ。
テリオンは今までの人生、食えるか食えない、美味いか不味いかくらいでしか判別してこなかった。それをこの歩く辞書のような男は豊富な知識と言葉で表現し、テリオンの知恵となるよう教示する。出会ったばかりの頃はこの長い講義を鬱陶しいとしか思わなかったが、今ではこの時間が無性に心地よい。
「そいつは?」
「シュー生地の菓子だ。中にジャムとクリームが入っている」
サイラスが手に持った菓子はたっぷりとクリームが挟まっており、見るからに甘そうだ。
「あんた、案外甘いもの食うよな」
「頭を使うとどうも身体が糖分を欲するようでね。甘い菓子や果物はよく食べるよ。食べ物と体の働きの関係性は、薬師と共同で研究している学者がいてね……」
「……その割に食うのは下手くそだがな。クリーム落ちるぞ」
「わっ……、おっと!」
ぼとりと落ちそうになるクリームをサイラスは寸でのところで抑える。落ちるのは回避したが、手はクリームで汚れてしまった。
「……べとべとだ」
「話しながら食ってるからだ」
クリームまみれのサイラスの手をぐっと握り引き寄せる。ペロリと指先に付いたクリームを舐めると、サイラスは分かりやすく動揺の声を上げた。
「て、テリオン……!」
「ん、甘いな」
「キミはまったく……これだけ人がいる場所で油断も隙きもない」
「油断も隙きもありすぎなあんたが悪い」
人がいるといっても他の客は目の前の食べ物に夢中で、テリオンとサイラスのことを見ている者は誰もいない。
握ったままのサイラスの手の甲へもう一つキスを送ると、ぽっと顔を赤くするものだから堪らなくなる。
「ま、まだべたつくから洗ってくるよ」
慌てて手洗い場を探しに行くサイラスを傍観し、可愛いヤツだとほくそ笑みながら、テリオンは残りの串肉を貪った。
◇◇◇
まったくテリオンは。
まだ頬が赤いのではないかと顔まで洗ってきてしまったではないか。多少のことでは動じない自負はあるつもりだが、どうもテリオンの一挙一動には翻弄されてしまう。からかわれているのは分かっているものの、彼がふふんと口角を上げる様を見るのも嫌ではなくて、何も言えなくなる。
頬を冷やしてもまだ体温が高い気がしたものの、テリオンを待たせてもいけない。足早にテーブル席へ戻ると、彼はエールを追加して待っていた。
再び食事と会話を楽しんでいると時間はあっという間で、いつの間にか帰り始める客もでてきた頃合いになっていた。
結局テリオンが特別好きな食べ物は分からず仕舞いだったが、無理やり探り出すものでもなかろう。久しぶりの遠出で良い旅だった、それで十分だ。
「そろそろ船の方に戻ろうか」
とはいえ帰りの便までまだ時間がある。競売場から波止場まで、店を覗きながら戻ることにした。 先程取り置きしたブラックエール。それから瓶詰めジャムやピクルス。持ち帰って家でも食べられそうなものを買い足していった。
めぼしいものは買い揃えたと思ったところで、ふわりと甘く芳ばしい香りが漂ってきた。
「良い匂いだ。どこの店だろう……ん、テリオン?」
「こっちだ」
後ろにいたはずのテリオンを見失ったと思えば、彼は学者のローブの袖をひっぱり、サイラスの前を歩いていた。ずんずん進むテリオンは、迷わず香りがする方へ向かっている。
「キミが先導するのは今日初めてではないかい? それにこの蜜のような香りはもしや……」
サイラスが推理する前に、テリオンは足を止めた。
目の前は焼き菓子店のようで、元気な婦人が呼び込みをしていた。
「焼き立てのショソンオポムはいかがー! 今日最後の焼き立てだよー!」
店先には手のひらサイズで葉っぱのような形をしたパイ菓子が並んでいる。甘い香りの発生源は間違いなくここだった。屋台の奥に焼窯があるようで、焼き立てが出されている最中だ。
「リンゴのパイか。帰りに食べるには少々重いが……この香りには抗えないな」
「だろ?」
「ふむ、キミはやはりリンゴが好きか。マダム、2つ頂けるかな?」
「いや、4つくれ」
「え、私は2つも食べられないが……」
「俺が食う分だ」
「ま、まだ食べるのかい?」
今日はテリオンの好きなものを好きなだけ奢る予定だったのだから、いくつ買おうが構わない。だがここにきてやけに食い気味に喋る様子に少し驚いてしまった。
「はい、4つね!」
店の婦人はすぐに4つ掴んで袋へ包んでくれた。サイラスが代金を支払うとテリオンはさっと受け取って、一つをサイラスへ差し出した。
温かい出来立てのパイを一口齧ると、中身も熱々でリンゴの甘みが口いっぱいに広がった。
「美味いな。生地はサクサクで中のコンポートはとろけるようで……リンゴも上質なものを使っているね」
サイラスがじっくりと味わっている間にも、テリオンは黙々と2つ目のパイに噛りついていた。彼の横顔は髪に隠れて表情がよく見えないが、よほどこの菓子が気に入ったらしい。
言葉や表情で感動を表現しなくともテリオンは案外分かりやすい反応をする、とサイラスは思う。夢中で頬張る様を見て、サイラスも満足げに笑った。
「これが食えただけで、今日来た甲斐があった」
「ふふ、それは良かった。キミの喜ぶ姿が見れて、私も来た甲斐があったよ」
テリオンが好きな食べ物も改めて知ることができた。
酒と食料が詰まった袋を抱え、甘いリンゴのパイを堪能しながら機嫌良く、二人はグランポートを後にした。
――そして後日、どうにかあのショソンオポムを作れないかとサイラスが壮大な実験を始めたので、二人の暮らしに”平穏”の二文字は当分訪れそうもなかった。