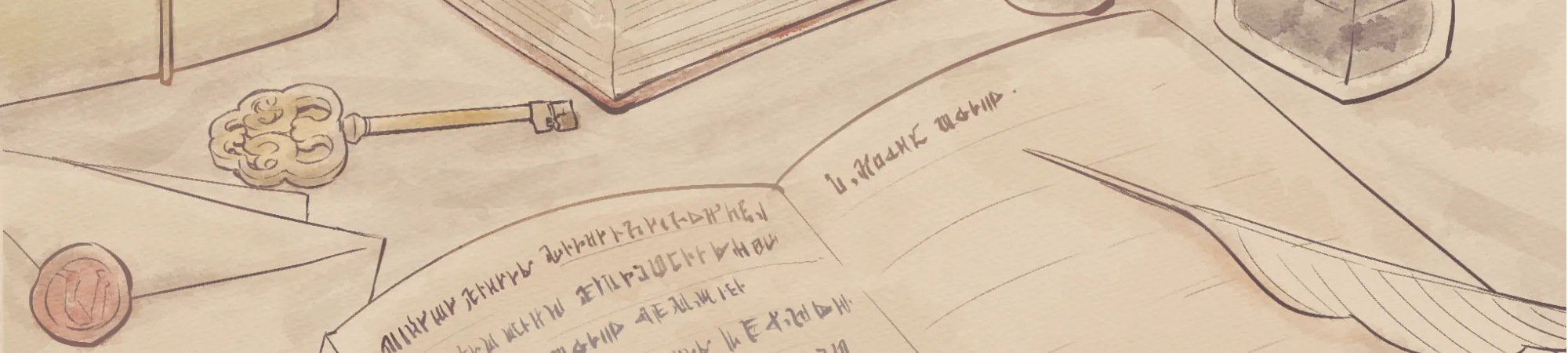現パロならテリオンは某番組の金庫の鍵開け職人みたいな仕事してそう、からスタートした現パロ。
テリサイのつもりで続きは考えてますが現状ただの仕事付き合いカプ未満。
続きはのんびり書く予定なので、のちのち加筆修正する可能性あり。
大学という施設は無駄にでかくて駐輪場から建物までの距離が長いな、といつもテリオンは思う。バイクの鍵をポケットに突っ込みながら、長い外通路を歩く。
彼は学内の者ではなかったが、ずけずけと入ったところで気にする者はいない。年齢的にここの学生と思われているのかもしれないが、残念ながら進学する金と受験資格がないのでそうではなかった。
部外者のテリオンが向かうのはこの『人文学部 史学科 研究室C』とプレートに書かれた部屋だけだ。 それほど広くはない室内は、相変わらず古い紙の匂いと珈琲の香りが充満している。本棚と本棚に挟まれるように置かれた机の前に、この部屋の主は座っていた。
「サイラス」
「やあ、テリオン君」
椅子に腰掛けている学者先生――サイラスは、涼しい顔で古めかしい本を読んでいた。似たような古書は机の上にも本棚の上にも積み重なっている。どれもいつもの光景だ。
「キミが来たということは、金庫の依頼が入ったのかな?」
「来月、最初の週末だ」
「少し待ってくれ、予定を確認しよう」
サイラスはデスクトップの方を向き、スケジュールを確認し始めた。
テリオンの方は勝手に小型の冷蔵庫を開け、紙パックのリンゴジュースを拝借する。好きに飲んでいいと言われたことはないが、飲むなと窘められたこともない。ストローを突き刺して飲み始めていると、予定を確認し終えたようだ。
「……うん、研究大会はその次の週だ。その日は空いている、是非同行したい」
「依頼内容。今回は電話だったから会ってはいない」
画面から目を離して振り返ったサイラスへ、電話口でとったメモを渡す。一読して依頼人の名前と住所を確認すると、サイラスの目は輝いた。
「この家、知っているよ。有名な地主の家だ」
「はあ……あんたはいつも楽しそうだな」
「だって地主の家の開かずの金庫だ。きっと歴史的価値のあるものが出てくるよ」
「普通は金目のものがあるかどうかだろ」
依頼者だって、貨幣か換金できるものが入っているのを期待してわざわざ依頼してくるのだ。紙幣か権利書以外の紙っぺらが出てきて喜ぶ人間は、学者先生くらいだ。
「そう、金銭的価値があるもの以外は大抵廃棄されてしまう。だから捨てられる前に回収に行く必要があるのだよ、テリオン君」
「こっちは仕事だ。邪魔だけはするなよ」
「その言い方では私は仕事ではないことになってしまうよ。ただの紙切れと思うかもしれないが、大戦時代の資料は焼失しているものが多いんだ。それが頑丈な金庫の中で燃やされず残っているとなれば――」
「……仕事なんだか趣味なんだか」
いつもの長ったらしい講義が始まってしまった。歴史的価値だとか百年近くも前の時代の出来事だとか、そんなものはテリオンにはよく分からない。
熱弁する学者先生の言葉を右から左へ聞き流しながら、ずずずとストローを吸った。
***
そもそも、学生ではないテリオンがなぜサイラスの研究室へ立ち寄るようになったのか――それを語るには些か長くなる。
テリオンは普段、とある百貨店の隅にある合鍵と靴修理の店で働いている。
身寄りのないテリオンが養護施設を出る年になり、就職するとなった時に考えたのは手に職をつけることだった。とはいえ、高等学校すらまともに卒業していない未成年の就職先は限られてくる。
(……まあ、土建か靴磨きくらいしかないか)
思いついた二択のうち、なりゆきで靴磨きをすることになったが、結果的に土建の仕事よりも性に合っていたと思っている。大きな建造物を作るより、細やかな作業をする方が得意だった。
最初は靴磨きだけをしていたが、徐々に靴を補修する技術や合鍵作製の仕事も覚えた。それにつれ給料もそこそこ貰えるようになったので、仕事の腕を上げるのは苦にならなかった。
仕上がりさえよければ客は喜んで帰っていく。百貨店という立地もあって、大抵は身なりの良い常連客ばかりである。ニコニコと接客用の演技していれば、そう面倒事も起こらないというのは数年働いて学んだことだ。
そしてテリオンの仕事は店内だけで完結するものだけではない。鍵トラブルの駆けつけも仕事の一つだ。玄関の扉が開かない、空き巣に鍵を壊された、トイレや風呂に閉じ込められた――こういった出向く仕事は基本給にプラスして手当が付くから割がいい。 駆けつけサービスは緊急度が高い案件がほとんどだが、テリオンが得意とするのは稀に依頼される特殊な現場だった。
「多分先々代くらいの時に使っていた金庫だと思うんだけどねぇ……」
「となると……百年くらい前のものですか」
接客モードの敬語で対応しながら、メモをとる。
客は穏やかそうな老婦人。数か月前に夫が亡くなり遺品整理をしていたところ、倉庫の中で金庫を見つけたらしい。話を聞いて分かったのは、代々生地屋を営んでいる商家であること、開かずの金庫はおそらく二代前に店で使っていたものだということ。
「そう。だいたいそれくらいの……ああ、写真も撮って持ってきたのよ」
「拝見します」
写真を受け取ると、見たことのあるタイプの金庫だった。鍵の内部が壊れていなければ、開けるのにそう時間はかからないはずだ。
「鍵も番号も分からなくって。ここのお店ならそういう金庫も開けてくれるって知り合いから聞いたの」
「ええ、保存状態は悪くないようですし、大丈夫ですよ。後日お伺いします」
愛想の良い対応も、今や慣れたものだった。
*
その仕事を受けた週末、依頼人の家に到着するとその門構えに圧倒された。相当歴史のある商家のようだ。
がっしりとした門構えだったが、遺品整理で出入りが多いためか入口は開いていた。覗いてみると、倉庫の前でパタパタとはたきを持って埃を払っている男がいた。
掃除をしているだけなのにやけに立ち姿が目を引くのは、俳優かと思うほど端正な顔立ちだからか、身に着けている服が上等なものだからか。テリオンには手が届かない代物だが、百貨店で働いていれば毎日のように上質な衣料品を見ているから分かる。
何者なのか分からない男に声を掛けるか迷っていると、あちらの方が先に声を掛けてきた。
「おや、例の鍵開け職人さんかい? 少し待っててくれ、家の人を呼んでくるよ」
男は掃除を中断して、奥の邸宅へと向かっていった。掃除をしていたということは使用人なのだろうか。いや、それにしては身なりと態度がおかしい気がする。
暫くすると、以前店で依頼してきた老婦人が共にやってきた。倉庫の中に案内されると、部屋の隅にどっしりとした金庫が鎮座していた。テリオンの胸くらいまで高さがあるそれは精巧な装飾が施されており、たとえ中身が空でもアンティーク品として値打ちがありそうだった。
「鍵屋さん、今日はよろしくお願いね」
「婦人、私も見学しても良いかな?」
「どうぞどうぞ、先生」
センセイ?
やはり使用人ではなかったらしい。商家がそう呼ぶならば士業の先生なのか、はたまた政治家先生なのか? 気にはなったが、さっさと終わらせて帰りに美味い飯屋にでも入りたい気持ちの方が勝った。
工具箱を床に置き、金庫と対面する。まずはロックスコープを取り出し、鍵穴を覗く。
(……開いてるな)
鍵は見つからないと聞いたが、開錠されたままのようだ。
(問題は……ダイヤルの方か)
ダイヤルはしっかりロックがかかっている。しかし難しい様式ではない。この金庫の型番ならば当たりの番号に合わせた時、僅かに音が変わる。聞き逃さないように耳を澄ませ、ゆっくりカチ、カチとダイヤルを回していく。
(最初の番号は……5……)
「なるほど、そうして音と感触で判断するのだね」
(……音で判断しているとわかっているなら静かにしてくれ)
後ろで見学している男はずっとぶつぶつと喋りながら関心している。ちっ、とわざと聞こえるように舌打ちをしてやったが全く意に介していない。金庫が開かないから苛立っていると思われてるのだろうか。あんたが邪魔なだけなんだが?
睨みつけてやったが、怯むどころか早く開けてくれと言わんばかりの期待した顔で立っている。年上だろうに、子供のように目を輝かせているこいつは一体なんなんだ。相手をするのも馬鹿らしくなってきて、一つ深呼吸をしてダイヤルに向き直す。
二つ、三つ、四つと、残りの番号も順調に見つけると、最後にガチャンと錠が開く音がした。
「お、開いたのかな?」
後ろに立つ男を無視して、依頼人である老婦人に向けて終わったことを告げる。
「まあ、もう終わったの?」
テリオンの仕事は鍵を開けるところまで。中身の確認は依頼した本人にしてもらうのが決まりだ。とはいえ金庫の中に更に鍵がかかった引き出しや小さい金庫がある場合もあるから、確認が終わるまで立ち会う。
ここまでして中身が空っぽなことは多々ある。しかし今回は無駄骨ではなかったようだ。
出てきたのは大量の帳簿と紙束。そして案の定、手提げ式の小さな金庫も入っていた。こちらは少しのピッキングで難なく開けることができ、入っていたのは釣銭に使っていたと思しき硬貨束だった。
「うちの親戚みんなで開けようと試してみたけど全然ダメだったの。やっぱり職人さんはすごいわね。貴方に頼んでよかったわ」
そう喜ばれるとテリオンだって悪い気はしない。作業代を貰い、帰ろうと振り向くと、先ほどまで後ろに立っていた男は地面にしゃがみ込んでいた。どうやら男は紙束の方に興味があるようで、テリオンが小さい金庫を開けている間、ずっと書面を読んでいたらしい。
「先々代とこれは……陸軍大佐との書簡か。金庫に残してあるということは、よほど重要な取引だったのだろうか……」
まだ何やらぶつぶつと独り言を喋っているが、テリオンの知ったことではない。男の横をさっさと通り過ぎようとしたところで、「待ってくれ」と急に足を掴まれ、ぎょっとした。
「あの頑丈な錠を容易く開けるとは、素晴らしい職人技だった。キミはこうして古い金庫を開ける仕事をしているのかい?」
「……人のことを探る前にすることがあるだろ。おたくはなんだ、この家の人間じゃないんだろ?」
「ああ、失礼。名乗るのが遅れたね」
男は立ち上がるとベストの胸ポケットから革のケースを取り出し、名刺を手渡してきた。文字だけのシンプルなそれに印刷されていたのは国立大学の名称、そして准教授という肩書。
「私はサイラス・オルブライト。大学で史学を教えている」
センセイとはそのまま教師の意であったこと、そしてこの学者先生はフィールドワークの延長で遺品整理を手伝っていたことを、この時ようやく知ることとなった。
*
その後、その名刺はすぐ紛失した。
妙に印象に残る変な男だったが依頼人ではないのだし、連絡先を残しておく必要もない――そう思っていたが、再び別の依頼先で鉢合わせるとは思わなかった。
その日もつつがなく仕事を完遂し、帰ろうとしたところで「次に金庫の鍵開けをする時は、私を呼んで欲しい」とまた名刺を押し付けられた。
無視することもできたが、二度あることは三度あるという言葉がある。鍵開けの仕事を続ける限り、また依頼先でバッタリ会う予感しかしなかった。
仕事として金庫の鍵開けを請け負うテリオンと、名家に眠る史料を求めるサイラス。目的地が一緒なのだ。
だからいっそのこと、学者先生の知識と人脈を利用することにした。互いの情報を共有すれば、テリオンは割の良い仕事の依頼が増える、サイラスは近代史の研究が進む。利害は一致していた。
***
斯くしてテリオンは古い金庫の鍵開け依頼が舞い込んできたときは、決まってサイラスの研究室を訪れるようになったのだった。
「この間は助かったよ。バイク旅も楽しいものだね。車とは違った景色で、未知の体験だったよ」
「タンデムの味を占めるな。乗りたいなら自分で運転しろ」
あんたが車検で足がないと言うから、この前は仕方なく後ろに乗せたんだ。運転する側は神経使うというのに、この男は景色を眺めるのに夢中で、バランスを取るのが大変だった。
「ふむ、キミとツーリングも悪くはないね。今度乗り方を教えてくれるかい?」
「は? なぜそうなる?」
いけしゃあしゃあとのたまう笑顔は何も考えていないのか、それとも学者先生なりの思惑があるのか――未だに腹の底が見えない。
サイラスに依頼内容を伝えたのだから、今日の用事は済んだ。空になった紙パックをポイとゴミ箱に投げ入れて、研究室の出入り口へ向かう。
「次はあんたの運転だからな」
「ああ、助手席も片付けておくよ」
バイクの後ろに乗せた代わりに、次はサイラスが車を出すと取り決めていた。
前にもサイラスの車に乗ったことがあったが、座席の上まで本だらけで、運転席以外は埋まっている有様だった。座席に積み重なった本をトランクに移動する重労働をする羽目になって散々だった。
「……車検に出したんだよな?」
「その時はもちろん片付けたよ。だけど家でも研究室でも使う本がたくさんあってね……」
「片付けろよ」
「うん、キミの手は煩わせない。それではまた、来月」
その言葉、本当だろうなと内心疑いながら、テリオンは呆れ顔で部屋を去った。
どうせ助手席だけ綺麗にして後部座席は本だらけに決まってる――そう予測がつく程、そこそこ付き合いが長くなっていることにまた大きくため息を吐いたのだった。
2022.2.10 up