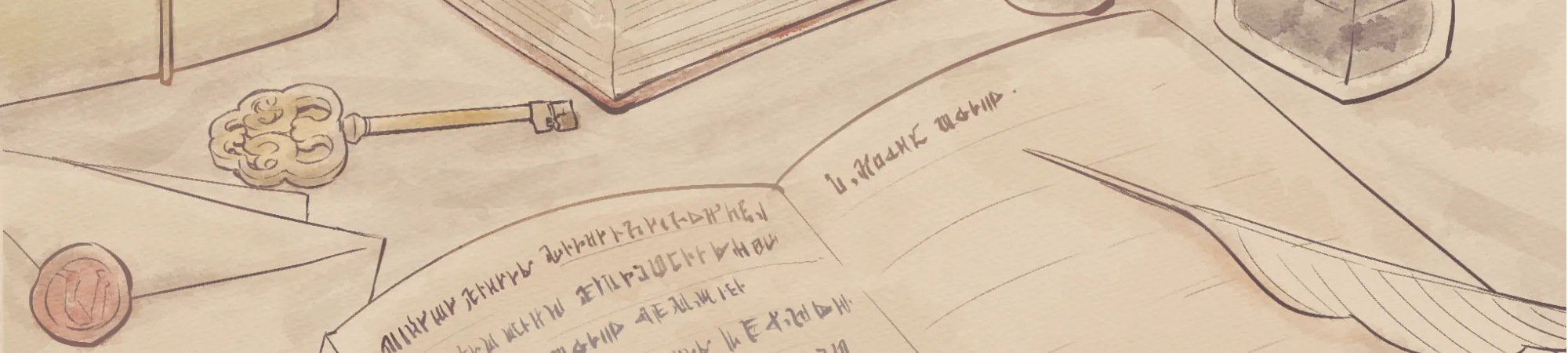「まったく……雨の日に出歩くからですよ」
「許せミシャ……とは言えんな、面目な……っ、ゴホッ!」
「回復するまで安静にお願いします」
アルロンドは珍しく病床に伏していた。発熱と喉に痛みがある。熱のせいで倦怠感がひどく、今日は寝台から一歩も動けそうになかった。
一昨日、庶民に扮して町に繰り出した帰りに雨が降ってきてしまった。雨具も持ち合わせておらず急ぎ足で帰宅したのだが、その時に身体を冷やしたのが悪かったのだろう。先ほど来た抱えの薬師は「最近町で流行っている喉風邪でしょう」と調合した薬を置いていった。薬を飲んで、休養を取れば数日で回復するだろうとのことだった。
喉の痛みのせいで固形のものは食べられそうにない。優秀な執事であるミシャはそれを察して果物をいくつか持ってきていた。ブドウ、プラム、オレンジと色とりどりの果物が籠に入っている。
「すりおろしたリンゴは食べられそうですか?」
それなら口にできる、と頷くとミシャは籠に入ったリンゴを一つ掴む。
「どのくらい召し上がれそうです?」
二切れ、の意味で二本の指を見せると「承知しました」とミシャは果物ナイフを持ち、その場で皮を剥き始めた。するすると瞬く間にリンゴの皮は紐のようになっていく。果実を六つに切り分け、ミシャはそのうちの二つをおろし金で手早くすりおろしていった。最後に瓶から蜂蜜を二匙ほど取り出して混ぜれば完成だ。
「どうぞ、召し上がってください」
匙で掬い上げ、口元に差し出される。冷たくシャリシャリとした食感が、熱っぽい身体には心地いい。
「商談や来客は断っておきますので、ゆっくりお休みになられて下さい」
ミシャは安心させるように優しく微笑んだ。その後も彼は冷たいタオルを額にのせてくれたり、こまめに飲み水を用意してくれたりと甲斐甲斐しく世話を焼いてくれたのだった。
***
「うむ。熱なし、喉の痛みもなし。復活だ!」
発熱してから三日後。
今朝はすがすがしい目覚めだった。身体も軽い。高らかに声を出しても平気だ。
(ミシャのおかげだな……)
そういえばミシャがいない。普段ならば起床を見計らって部屋に入ってくるのだが。カーテンを開け、着替えの手伝いをしてくれるのが毎日のルーティーンだ。今日もまだ寝込んでいると思い、そっとしてくれているのだろうか。
食卓へ向かってもミシャはいなかった。流石に違和感を感じ、調理場へ向かう。料理人とメイドにミシャの所在を聞いても「今日はまだお見かけしておりません」と返ってくるばかりだった。
執事がいなくとも朝食の準備が滞りなく進んでいるのは、普段のミシャの監督が行き届いている証拠である。だが調理場にも顔を出していないとすると。
(……もしや)
ミシャの部屋は調理場の近くにある。食料と酒と食器を管理するのに都合が良いからだ。すぐさま向かうと、悪い予感は的中していた。
「コホッ、ア、アルロンド様……」
「やはりうつしてしまったか」
部屋の奥では寝巻きのままのミシャがベッドで横になっていた。いつもより声が低く掠れている。喉の痛みによる咳込み、起き上がるのも億劫な様子。昨日までのアルロンドと同じ症状だ。ずっと看病してくれていたのだから、うつるのも当然であった。咄嗟に起き上がろうとしたミシャの肩を押して再び寝かせる。
「治るまでしっかり休めミシャよ。今日は私を頼ってくれ。君のおかげで私はすっかり元気だからな」
「いえ、ゴホッ、……っ、主に世話をさせるなど……」
「うつしてしまった詫びをさせてくれ。そうだ、リンゴをすりおろしてくれたな。あれを用意しよう」
手をつけていなかった果物が自室に置いたままであったのを思い出して、一度ミシャの部屋を出た。
——の、だが。
はて、リンゴとはどうやって剥くのか。
果物籠の中にある赤い果実を手に取り悩む。人生で一度もリンゴの皮を剥いたことがなかったことに、今気付いたのだった。
ミシャが先日どうやって皮を剥いていたか、記憶を手繰り寄せてみる。確か果物ナイフを当て、実を回転させながら皮を剥いていたような。真似てみようとナイフを果実に当て、刃を差し込もうとしたところで……ミシャのように器用にできないだろうと考えを改めた。誤って指を切ろうものなら更に心配をかけてしまう。焦るミシャの顔が脳裏に浮かんだ。
慣れないことは無理にするものではない。アルロンドはひとまずナイフを置いた。果物籠の隣に置かれている蜂蜜瓶の中身が少ないことにも気付く。
丸いままのリンゴと向き合って暫し思案する。それから庶民の服に着替え、果物籠を抱えて町へと向かった。
***
「ミシャ、具合はどうだ?」
「アルロンド様……ッ、ケホッ!」
用事を済ませてミシャの部屋に戻る。相変わらず咳があり、この短時間ではあまり症状は変わっていなさそうであった。
「喋らなくていい。安静にしていろ」
「申し訳、ありません……」
「謝るな。ほら、作ってきたぞ。私一人ではリンゴも切れなかったがな!」
ミシャは必要以上に声を出さなかったが(町に行ってきましたね……病み上がりなのに……)と眉根を寄せて顔で訴えていた。ミシャが予想した通り、商人街で蜂蜜を買い足し、薬師から薬を買い、その足で酒場に行ってマスターに調理を手伝ってもらった。その成果が今手元にある、蜂蜜を混ぜたすりリンゴだ。
「許せミシャ。ほら」
すりおろしたリンゴをスプーンで掬う。ミシャの口元まで持っていこうとすると、手で遮られてしまった。
「あの……さすがにそのようなことは……」
「遠慮するな。君も私にこうしてくれただろう?」
「ですが……」
「甘えろ、ミシャ」
何度か渋ったミシャはようやく「……そう、させて頂きます……」と手を避けてくれた。
リンゴの皮が剥けなくとも、寄り添うことはできる。またコホコホと咳込むミシャの背中を撫でた。
***
「アルロンド様、ご迷惑をおかけしました。今日から復帰致します」
アルロンドが三日ほどで回復したのと同じように、ミシャもまた数日で復調できた。アルロンドの起床を見計らって部屋に入ってきたミシャは、普段通りの身のこなしだった。手際よく部屋のカーテンを全て開け、アルロンドの着替えを手伝い、朝食の給仕まで完璧にこなす、いつものミシャだった。
その後は先延ばしにしていた来客の対応をしているうちに、時間はあっという間に昼下がりになっていた。
アルロンドがソファに座り、一つ伸びをすると「お茶の用意を致します」とミシャはすぐにティーセットと焼き菓子をワゴンに載せて戻ってきた。
ポットの中身がカップに注がれると、ふわりとハーブの優しい香りが広がる。
「カモミールか?」
「はい。病み上がりですのでハーブティーをご用意しました」
「そうか。ならばミシャも飲むといい」
病み上がりはミシャも同じだ。ならば共に茶を飲もうと、ソファの隣に座るよう促す。しかしミシャは困り顔をして首を横に振った。
「……アルロンド様、私は業務中ですので」
「じゃあ私と一緒に茶を飲むのが仕事だ、ミシャよ」
自分でも良くない言い方であるのは分かっているのだが、こうでもしないと頑なにミシャは従者の姿勢を崩してくれない。もっと肩肘張らずに接してくれても良いのだが、その真面目なところがミシャの長所でもある。
もう一押しのつもりで再度ソファの空いている座面を叩いた。
「まったく……あなたという人は……」
そう肩をすくめながらも、ミシャはもう一つティーカップを手に取ってハーブティーを注いでいく。ついでに先日買ってきた蜂蜜も入れて。二つのティーカップをテーブルに置くと、ようやくミシャは隣に座ってくれたのだった。
ミシャが座ってくれたことに満足してティーカップに口を付ける。カモミールの優しい香りと共に、蜂蜜の甘い味がした。
2024.12.31 up