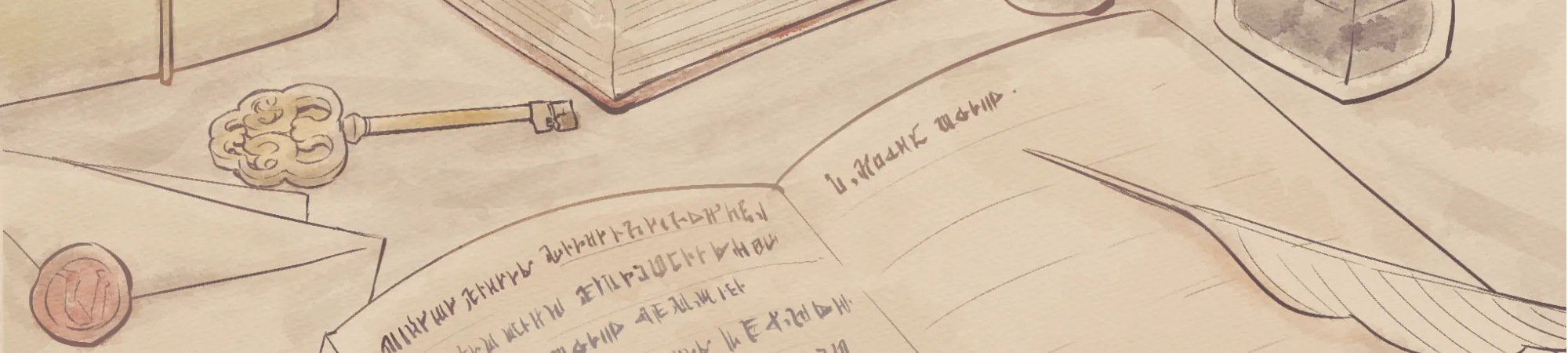テリ→サイ。
本編終了後の話ですが、特にネタバレはないはず。
書籍名は全部捏造。
「テリオン、また窓から入ってきたのか」
教務が終わり学院の研究室へ戻ると、窓が開いていた。
サイラスは今朝、戸締りをして部屋を出たはずだ。だから開けたのは勝手に侵入し、椅子を占領しているこの白い髪の青年である。
「守衛に見つかって面倒事になったらどうするんだい?」
「そんなヘマはしない」
鍵開け用の針金束を人差し指でくるくると回しながら、テリオンは用件を切り出した。
「読み終わった。次のはあるか?」
「ああ、確かこの辺に……」
机の上には生徒達への課題とサイラス自身の研究資料が山積みになっている。乱雑としていてもサイラス本人はどこに何があるかは把握しているので、目的のものはすぐに見つかった。
「はい、『カラクリの匣』の2巻と『東方の郷』だね」
前者は一筋縄では開かない仕掛け小箱の作り方の書。後者はとある冒険家が書いた、東方の異国にあるという隠密行動を得意とする者が住む集落の話だ。
8人での旅を終えた後も、テリオンはたまにこうして数冊本を借りに来る。読み終わるとアトラスダムに来て本を返し、また新しい本を借りてはどこかへ行くのだった。
アトラスダムの図書館は、開架エリアならば身分問わず誰でも自由に出入りできる。彼が好きな本を借りられるように手続きもした。
しかし彼は自分で図書館に赴くことはなく、こうしてサイラス経由で借りていく。本のタイトルをテリオン自ら指定してくることもあるし、サイラスが選書して渡すこともある。
テリオンがどのような本に興味を持ってくれるか。それを考えるのは楽しい。返却する時に必ず短いながらも感想をくれるので、本から得た知識が彼の糧になっているのを実感する。
サイラスが渡した2冊を受け取ると、テリオンは前回借りていった本を返却した。その上には、何やら小洒落た物体が乗っていた。
「あんたにやる」
それは手のひらサイズの木箱だった。今しがた返却してもらった『カラクリの匣』第1巻の表紙に描かれている絵と似ている。
「もしかして、キミが作ったのかい?」
彼は頷いて、挑発的な笑みを浮かべた。
「解いてみろよ、学者先生」
「ほう、興味深いね。受けて立とう」
どうやら本に書かれていた仕掛け箱を模して作ったらしい。このパズルのような箱を開けてみろ、と出題してきたわけだ。
「キミは盗賊として、宝箱や金庫の構造を知るためにこの本に興味を持ったのだと思ったが……まさか作ってしまうとはね」
「実物があった方がつくりが分かる」
「そうだね、こういった立体物は平面図では構造が分かりにくいことも多い。しかし随分精巧に作ってあるね。工芸職人も向いているのではないかな?」
「ただの暇つぶしに作っただけだ。ソレばかり作るのは勘弁だな」
本人はそう言うが、かなり凝った寄木細工が施されている。職人技と称賛しても過言ではないだろう。
「ふむ……、中には何が入っているのかな?」
傾けるとカタカタと音がすることから、何かしら入っているのだろう。
「開けられたら、中身もあんたにやる」
それだけ言って、テリオンは借りた2冊を手早くブックバンドに括り付けて、やはり窓から去っていった。
占領されていた椅子に座り、改めて手のひらにあるものを観察する。
”箱”である通り、この物体には6つの面がある。しかしどこが蓋で中身が取り出せるかは分からない。6つの面には木のパーツを組み合わせた幾何学模様が施されている。このパーツはスライドして動かせるようだ。これらを正しい順序で動かせば、箱が開くという仕組みだろう。
テリオンが先ほど返却した本と照らし合わせてみても、仕掛けにアレンジが施されているようで、一筋縄では解けないようになっていた。もっとも、書いてあるまま作ったのであれば出題にならないともいえる。
これは手強いな、とサイラスは本腰を入れた。メモ用紙とペンを取り出し、一つ一つパターンを試して記録していく。
何度か試行錯誤を重ねると、当たりと思われる順序が見えてきた。
右、上、右、左……と木製パーツをスライドさせていくと、カチと小気味よい音がした。箱全体を傾けると蓋の部分が開き、中に入っていた物が現れる。
「ブローチ……だね」
翡翠だろうか。楕円型で艷やかなルースに仕立てられたそれは、透明度も高い。翡翠はありふれた輝石だが、純度が高いものは高級品だ。魔力を高める装身具としても重宝されているが、あまり出回るものではない。
台座の装飾も華美すぎず、ローブの留め具にするのに丁度良いサイズだ。有り難く使わせてもらおうと、ローブ留めを付け替えた。
共に旅をしていた時も、魔力を高める装備が宝箱から出てきた時は「これならあんたの方が使いこなせるだろ」と譲ってくれることが多々あった。これもそういった類のものだろう。
遠くの壁に向かって手を掲げると、一瞬にして全ての燭台に灯がともる。うん、魔法の調子も良さそうだ。
テリオンは一つの場所に留まらない。しかし必ずまたアトラスダムに来てくれる。
その時までにまた彼が興味を持ちそうな本を揃えておこう。次はどんなジャンルにしようかと考えながら、サイラスは研究用の資料を広げ始めた。
***
また二か月ほど経った頃、テリオンはアトラスダムへやってきた。
「今日も窓から来たね。盗みに入るわけではないのだから、正面から入って良いのだよ?」
そう再三訴えるサイラスの胸元には翡翠の装飾が輝いている。
テリオンはそれを見て、目を細めたのだが―――その瞳とブローチが同じ彩であることにサイラスはまだ気が付かない。
彼が、盗みたいと渇望するものにも。